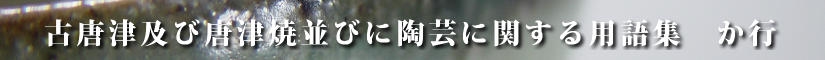古唐津及び唐津焼並びに陶芸に関する用語集 「こ」
こ
古伊万里(こいまり)
明治以前に作られた伊万里焼で、特に赤絵(あかえ)が完成して以降のものをいう。それ以前のものは初期伊万里と呼びます。
「古伊万里」(こいまり)とはその名のとおり古い伊万里焼のことをさし、通常は江戸時代の伊万里焼を称しています。
染付(そめつけ)の藍色の素地に、上絵の金、赤、緑、黄色などで装飾した作品を「古伊万里様式」と呼んでいますが、藍色と金、赤の組み合わせが基本で、金欄手(きんらんで)の古伊万里と呼ばれることもあります。
「古伊万里様式」は、それまで流行していた「柿右衛門様式」に替わり、元禄期(1688~1704)に生まれています。
「柿右衛門様式」同様にヨーロッパで好まれ、元禄から享保(1716~1736)にかけて大量に輸出されました。
余白がないほど文様が描きこまれた絢爛豪華な作品もあり、豊かな時代の元禄時代を反映しています。
構図の特徴は、器を放射状の直線や唐花(からはな)状の曲線で区別し、窓絵(まどえ)と地文様(ぢもんよう)を交互に描きます。
文様には唐花文(からはなもん)、獅子牡丹文(ししぼたんもん)などがあります。
口縁(こうえん)
蓋がついていない器の、一番上にあたる縁の部分の周辺のこと。
香合(こうごう)
香を入れるために使う、蓋付きの小さい器で茶道具のひとつ。
口唇(こうしん)
器の一番上のへりにあたる部分のこと。
高台(こうだい)
糸底(いとぞこ)ともいいます。器を安定させるために底につくられた台。
同じ土で後からつける付け高台と、削り高台の2種の技法があります。
唐津焼の高台の種類について、
唐津焼の高台には作為の有る・無しに問わずいろんな種類がありますが、
そんな高台を先人たちは色々な名称で楽しみ鑑賞してきました。
竹節高台(たけふしこうだい)
二重高台(ニジュウコウダイ)
三日月高台(ミカヅキコウダイ)
藁敷き高台(ワラシキコウダイ)
貝高台(カイコウダイ)
貝殻高台(カイガラコウダイ)
竹節高台「たけふしこうだい」
略して竹の節とも言う。
茶碗の高台が竹の節状になったものを言う。
井戸茶碗の約束の一つになっているが、その他の朝鮮茶碗や唐津茶碗の特色でもあり、茶碗の一景色とされる。
二重高台(ニジュウコウダイ)
輪形につくられた高台の畳付の面に、さらに一筋の溝を彫ったもの。
志野焼・唐津焼などに見られます。
三日月高台(ミカヅキコウダイ)
高台畳付の幅が均等にならず幅が狭い所があったり広い所があったりちょうど月の形「三日月」に見立てて、何時の時かそう呼ぶようにらしい。
昔の技術が下手だった訳ではなく、蹴り轆轤のすわりが悪かったり芯がずれたりした為と思われます。
今では許され難いことでも昔の茶人は洒落で心地よい名前を付けたり、それでも良しという作り手のおおらかな時代に惹かれますね。
高台敷き高台(ワラシキコウダイ)
備前焼の火襷と類似しています。
焼く工程で他の器物と溶着しないよう器物の間に藁を敷いて焼くが、その藁の跡が付いたものを言います。
又、藁の代わりに籾殻を強いて焼くときは籾殼高台といいます。
付け高台(つけこうだい)
高台を、ロクロの上で削り出すのではなく、あとから粘土でつくった紐を輪にして貼りつけたものをいいます。
交趾焼(こうちやき)
中国明時代後期から清時代初期に作られた三彩陶。
交趾(こうち)(現在のベトナムの北部)の産と考えられたことが名前の由来です。
高麗(こうらい)高麗青磁(こうらいせいじ)高麗茶碗(こうらいぢゃわん)
朝鮮半島の高麗時代(918~1392年)につくられた陶磁器の総称。
高麗王朝期に生み出された青磁。
高麗青磁は宋朝の影響を受けてはいるが、下地に美しい彫刻をし、そこに独特の白土や黒土の象嵌をして模様を浮かび上がらせているのが特徴です。
高麗王朝は1392年に滅んで李朝の時代になるましたが、当時は李朝時代も異名として使っていました。
茶道における高麗茶碗はほとんどが李朝時代のものであり、高麗時代のものはほとんどありません。
井戸・割高台・呉器・半使・絵高麗・刷毛目・伊羅保・高麗青磁・三島・粉引・たまご手・堅手・金海・熊川(こもがい)・御本・柿の蔕(へた)・ととやなどに分類されます。
香蘭社(こうらんしゃ)
明治7年に設立された有田の磁器工場。輸出向けの大量生産を目指し、現在も有田の主要工場。
呉器(ごき)
李朝(りちょう)時代に作られ、見込が深く高台と丈の高い高麗茶碗の一種。。
御器・五器とも書く。
呉器の名は、形が椀形で禅院で用いる飲食用の木椀の御器に似ているためといわれる。
一般に大振りで丈が高く見込みが深く、高台は外に開いた「撥高台(ばちこうだい)」が特色とされる。
素地は堅く白茶色で、薄青みがかった半透明の白釉がかかる。
「大徳寺(だいとくじ)呉器」「紅葉(もみじ)呉器」「錐(きり)呉器」「番匠(ばんしょう)呉器」「尼(あま)呉器」などがある。
「大徳寺呉器」は、室町時代に来日した朝鮮の使臣が大徳寺を宿舎とし帰国の折置いていったものを本歌とし、その同類を言う。
形は大振りで、風格があり、高台はあまり高くないが、胴は伸びやかで雄大。
口辺は端反っていない。
古清水(こきよみず)
京焼の一種で、野々村仁清以後奥田穎川(おくだえいせん:1753~1811)以前のもので、仁清の作風に影響されて粟田口、八坂、清水、音羽などの東山山麓や洛北御菩薩池の各窯京焼諸窯が「写しもの」を主流とする茶器製造から「色絵もの」へと転換し、奥田穎川によって磁器が焼造され青花(染付)磁器や五彩(色絵)磁器が京焼の主流となっていく江戸後期頃までの無銘の色絵陶器を総称します。
幕末に五条坂・清水地域が陶磁器の主流生産地となり、この地域のやきものを「清水焼」と呼び始め、それ以前の色絵ばかりでなく染付・銹絵・焼締陶を含む磁器誕生以前の京焼を指して「古清水」の名が使われる場合もあります。
古九谷様式(こくたにようしき)
伊万里焼(いまりやき)の中の様式の一つ。作風は五彩手・青手・南京手の三つに大別。
黒釉(こくゆう)
黒色に発色する高火度釉。中国では漢代の越州窯(えっしゅうよう)ではじまり、日本では古瀬戸からはじまった。
五彩(ごさい)
白磁や白釉陶に、赤・緑・黄・紫・青などの明るい上絵具で文様を描いた中国の色絵(いろえ)。
呉須(ごす)
酸化コバルトを主成分し染付(そめつけ)に用いる彩料。釉(うわぐすり)をかけ焼成すると藍青色になり、鉄釉(てつぐすり)に加え上絵具(うわえのぐ)の青としても用います。
中国では青料といいます。
還元焔により藍色を呈し、酸化させると黒味を帯びます。
コバルト鉱が風化して水に溶けて沈殿し、鉄、マンガン、ニッケルなどの化合物が自然混合した天然のコバルト混合土。
これらの化合物が多いほど黒くなる。
日本では産地の浙江省紹興地方が古くは呉の国と呼ばれたため呉州(ごす)と呼び呉須と書いたとされます。
元朝(1279~1368)末に、西域よりスマルト(酸化コバルトを4~6%溶かし込んだ濃紺色のガラス)、中国で「蘇麻離青(そまりせい)」と呼ばれる鮮やかな青藍色を発する青料が招来し、景徳鎮で使われたが、明朝成化年間(1465~87)に輸入が途絶え「土青(どせい)」といわれる中国産の黒ずんだ青料が使われるようになりました。
明朝正徳年間(1506~21)からは、西アジアより「回青(かいせい)」と呼ばれる、明るい青藍色のものが輸入され、嘉靖(1522~66)、隆慶(1567~72)、萬暦(1573~1619)の青花に主として使われるようになりました。
呉須赤絵(ごすあかえ)
赤や緑を主に鮮やかな色で、奔放な花鳥文、魚文などが描かれた中国明代の後期に焼かれた色絵磁器。
赤・青・緑に、黒の線描きが加えられているのが特徴。
茶人に好まれ、桃山時代から江戸時代初期に大量に輸入されました。
御所丸(ごしょまる)
高麗茶碗の一種。
御所丸の名は、朝鮮との交易に使われた御用船を御所丸船といい、文禄・慶長の役のとき、島津義弘がこの手の茶碗を朝鮮で焼かせ御所丸船に託して秀吉に献上したことからきたと思われます。
桃山より江戸期にかけ日本から朝鮮に御手本(切形)を送って焼かせたものを御本といい、古田織部の御本で金海の窯で焼かせたもので「古田高麗」ともいい、御本としては最も古いものになります。
堅手の一種で「金海御所丸」ともいいます。
形は織部好みの沓形で、厚手。
腰には亀甲箆という箆削りがあり、高台は大きく、箆で五角ないし六角に切られています。
高台は釉がかからず土見せ。
白無地の「本手」(白手)と、黒い鉄釉を片身替わりに刷毛で塗った「黒刷毛」と呼ばれるものがあります。
古瀬戸(こせと)
瀬戸で生産された陶器のうち、鎌倉時代の初めから室町時代の中頃までの施釉陶器(せゆうとうき)を古瀬戸と呼びます。
従来、その起源は陶祖加藤四郎左衛門景正(通称藤四郎)による中国製陶法の招来とされています。
道元禅師が貞応2年(1222)、明全に従って宋に渡ったとき藤四郎が道元の従者として渡宋し、禅修業の傍ら逝江省の瓶窯鎮で製陶の修業をし、安貞2年(1228)帰国後、尾張の瀬戸に窯を築き、中国風の陶器を焼いたのが始まりと伝えられています。
近来は桃山時代以前の瀬戸陶磁器を古瀬戸と概称する場合があります。
「灰釉(かいゆう)」のみが使用された前期(12世紀末~13世紀後葉)、「鉄釉(てつゆう)」が開発され、素地土の柔らかいうちに印を押して陰文を施す「印花(いんか)」、文様をヘラや釘、クシ等で彫り付ける「画花(かっか)」、粘土を器体に貼り付けて飾りにする「貼花(ちょうか)」など文様の最盛期である中期(13世紀末~14世紀中葉)、文様がすたれ日用品の量産期となる後期(14世紀後葉~15世紀後葉)の三時期に区分されています。
前期の「灰釉(はいぐすり)」は、朽葉色の釉薬で戦前一般には「椿手(ちんしゅ)」と呼ばれました。
鎌倉後期以降の「鉄釉」は鬼板という天然の酸化鉄を釉薬に混ぜたもので、黒若しくは黒褐色に発色します。
今日、この黄釉若しくは黒釉の掛かったものも古瀬戸と称することがあります。
古染付(こそめつけ)
古染付とは必ずしも古渡りであることを要せず、今日では明末期に景徳鎮の民窯で特に日本向けに作られたと思われる独特の風趣のある器形や文様をいいます。
口縁部や稜線部などに「虫喰い」とよぶ釉はげが見られ、茶人には大いに好まれ日本に多く残存している。
民窯ならではの大らかさと独特の風雅な趣が見られます。
木葉天目(このはてんもく)
木葉天目は、中国江西省の吉州窯で焼かれた玳玻盞天目の一種で、黒釉面に実際の木の葉を貼り付け焼成されたものです。
この碗は、見込み中央から口縁にかけて木の葉の姿が茶褐色に発色して現れ、焼け縮みの多い部分は虫喰い状に欠失しています。
高台は吉州窯特有の黄白色の素地が見れます。
伝来は不詳となっています。
コバルト(こばると)
下絵具として使用される青色の発色剤。19世紀以降ヨーロッパから輸入され、現代食器に多用。
粉引(こびき・こひき)
粉吹(コフキ)ともいい、李朝期の朝鮮茶碗の一種。土・釉から慶尚南道産の三島刷毛目の類と考えられる。鉄分の多い土であるため、白尼を一面に化粧掛けしているが、その白尼の粒子がやや荒いため、さながら粉をまぶしたような肌に見えるのでこの名があります。
元来は、鉄分の多い土は焼くと黒くなりますが、白く見せるために胎土の上に白土を使って化粧する技術です。
粉引の場合は全体にかける為に化粧土を水に溶かした溶液の中に漬け込む方法か、柄杓で流し掛けする方法を行います。
窓見せとは、化粧土か釉薬がかかっていない部分を作る装飾技法の一つです。自然にできる場合と意図的に作る場合があります。
御本(ごほん)
「御本(ごほん)」とは、手本をもって作られたという意味です。
土の中に含まれている鉄分が窯(ようへん)変し、赤い色彩や斑点状の模様が現れること。
熊川(こもがい)
見込(みこみ)が深く、腹がゆったりとした丸みを帯び口縁はわずかに端反った高麗茶碗(こうらいぢゃわん)の一種。
熊川の名は、慶尚南道の熊川という港から出たもので、その近くの窯で出来たものが熊川から積み出されたためこの名があります。
「熊川なり」という形に特徴があり、深めで、口べりが端反り、胴は丸く張り、高台は竹の節で比較的大きめ、高台内は丸削りで、すそから下に釉薬がかからない土見せが多く見られます。
見込みの中心には「鏡」「鏡落ち」または「輪(わ)」と呼ぶ小さな茶溜りがつくのが一般的です。
また釉肌に「雨漏り」が出たものもあります。
「真熊川(まこもがい)」「鬼熊川(おにこもがい)」「紫熊川(むらさきこもがい)」などの種類があり、「真熊川」は、作風は端正でやや深め、高台も高く、素地が白めのこまかい土で、釉は薄い枇杷色、柔らかく滑らかで細かい貫入があります。
古人は咸鏡道(かんきょうどう)の熊川の産と伝えて、真熊川のなかで特に上手のものを、その和音を訛って「かがんどう(河澗道・咸鏡道)」とか「かがんと手」と呼でいました。
「鬼熊川」は、真熊川にくらべ下手(げて)で、荒い感じがあるのでこの名があります。
形はやや浅めで高台が低く、見込みは広いものが多く、鏡が無いものもあります。
時代は真熊川より下るとされています。
「紫熊川」は、素地が赤土で釉肌が紫がかって見えるものを指します。
御用窯(ごようがま)
藩窯(はんよう)のことで、江戸時代に藩が殖産や専用の製品を作らせるために開いた窯。